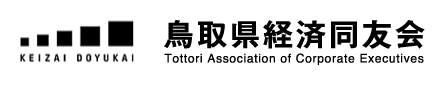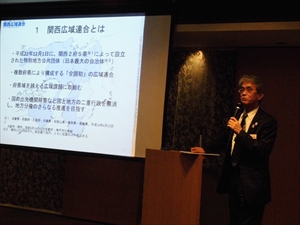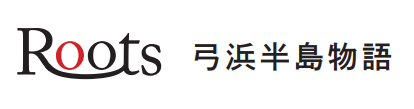3月10日(火)ホテルニューオータニ鳥取を会場とし、東部地区では内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局から菊地和博次長をお招きし、「地方創生にむけて~総合戦略策定と地方創生元年の動き~」と題してご講演をいただきました。
2015年は「地方創生元年」として位置づけられており、鳥取県ではすでに地域版総合戦略策定に向けて
着手しています。
地方経済・地域社会が抱える重要な課題が「超高齢化・少子化」であり、「雇用の場の創出」です。
県・市町村ではこの地域版総合戦略策定によって地域の抱える課題解決を図るべく、迅速に適格に対処していくことがもとめられており、経済界においても、連携を図りながらアクションを起こす必要があります。
この3月例会は、オープン例会とし、会員だけでなく県・市の職員、大学、一般の方にも参加していただきました。参加者全員熱心に耳を傾けてていました。出席者は63名。
菊地和博氏の講演内容は概ね以下のとおりでした。


(1)まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略」
【2020年までの基本目標・成果指標】
①「しごと」と「ひと」の好循環作り
●地方における安定した雇用を創出する。
若者雇用創出数(地方)⇒2020年までの5年間で30万人
若い世代の正規雇用労働者等の割合⇒15~34歳 92.2%(2013年の水準)
女性の就業率⇒73%
●地方へ新しい人の流れをつくる。
地方⇒東京圏転入 6万人減
東京圏⇒地方転出 4万人増
●若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。
結婚・妊娠・出産・子育てできる社会の達成ができていると感じる割合
40%以上(2013年では19.4%)
第1子出産前後の女性継続就業率⇒55%(2010年38%)
結婚希望実績指標⇒ 80%(2010年68%)
夫婦子供数予定(2.12)実績指標⇒95%(2010年93%)
②好循環を支える、まちの活性化
●時代に合った地域づくり、安心なくらしを守り、地域と地域との連携
地域連携数など目標数値は地方版総合戦略を踏まえて決定
(2)<しごとの創出>
①地域産業の競争力強化(業種横断的取組)
●包括的創業支援、地域イノベーションの推進、中核企業の創出・支援⇒雇用を約11万人創出
②サービス産業の活性化・付加価値向上⇒若い世代の雇用約6万人増
③農林水産業の成長産業化⇒活力創造プラン
・食文化・食産業のグローバル展開
・バリューチェーンの構築
・生産現場の強化
・多面的機能の維持・発展
・林業の成長産業化
・水産日本の復活
④観光の振興、地域資源の活用⇒観光業で若い世代雇用 約8万人
(3)<ひとの創出>
①地方への新しい人の流れをつくる。
●地方移住の推進⇒全国移住促進センターの開設、地方居住推進国民会議設置
●地方移転⇒地方にある企業の本社機能強化<税制上のインセンティブを与える。
●地方大学等の活性化⇒知の拠点として地方大学強化、地元学生定着、地域人材育成
②若者雇用対策の推進、正社員実現加速プロジェクトの推進
●新卒者等の就職支援、フリーター等の正規雇用化支援、若者のための総合的・体系的法整備
●非正規雇用対策
③結婚・妊娠・出産・子育て支援
●子育て世代包括支援センターの整備
●幼児教育の無償化など段階的に実施、教育費負担の軽減
●3世代同居・近居の支援
④仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現<「働き方」改革>
●育児休業の取得促進
●所定労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進
(4)<まちの創生>
①「小さな拠点」(多世代交流・多機能型形成支援)
●土地利用計画+s-ビスの提供体制 整備
施設の集約、交通・輸送や買物機会の確保、燃料の供給
福祉拠点の整備、地域コミュニティーの活性化、ICT利活用、公立学校の適正規模化
②地方都市における経済・生活圏の形成(地域連携)
●都市のコンパクト化と周辺のネットワーク形成
●連携中枢都市圏の形成、定住自立圏の形成促進
中心市——高度な医療サービス、圏域全体の経済をけん引
近隣市町村——地域密着の医療サービス、農業の6次産業化や観光振興
③大都市圏における安心な暮らしの確保
④既存ストックのマネジメント強化
●公共施設・公的不動産の利活用(民間活力の活用)
●インフラの戦略的な維持管理・更新の推進
●空き家対策の推進/中古住宅市場の整備
(5)地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開
情報支援——–地域経済分析システム整備
人的支援——–地方創生人材支援制度(小規模市町村に首長の補佐役派遣)
地方創生コンシェルジュ制度(意欲ある府省庁の職員を相談窓口に選任)
財政支援——-
●緊急的取組(H26補正)~経済対策~⇒地域住民生活等緊急支援のための交付金
地方創生先行型の創設——
①地方版総合戦略の策定
②しごとづくりの事業—-ex.UJIターン助成金、創業支援、販路開拓
これらは、H27も継続
③地域消費喚起・生活支援—–ex.プレミアム付商品券、灯油購入助成、
ふるさと名物商品・旅行券 など
◎税制・地方財政措置
◎H28年以降——–総合戦略に基づく取組展開
新型交付金の本格実施
(6)地方における具体的な取り組み事例
①島根県海士町の取組——-島をまるごとブランド化
②徳島県神山町の取組——-光ファイバー網完備、ITサテライトオフィスの誘致
③鹿児島県鹿屋市串良町小原柳谷集落(やねだん)の取組——–
遊休地でのカライモ栽培と販売、土着菌の製造・販売、カライモ焼酎「やねだん」、
空き家を「迎賓館」芸術家を招聘
④岩手県柴波町の取組——公民連携事業(PPP)~オガールプロジェクト
町有地0.7ha 駅前整備事業
オガール・プラザ整備など
⑤富山県富山市の取組——コンパクトなまちづくり着手~お団子(集積地)を串(公共交通)で結ぶ
LRTネットワーク(お出かけ定期券)、公共交通沿線地区居住促進 、中心市街地活性化