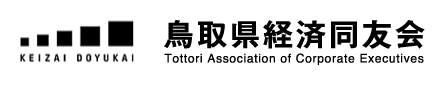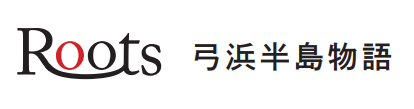12月20日(土)に教育問題委員会担当の教育フォーラムを開催しました。昨年度に引き続き第2回目となる今回の教育フォーラムでは、米子工業高等専門学校建築学科 学科長 玉井 孝幸 氏にご協力頂き、実社会に出る直前の同学科の3年生、4年生を対象に「コミュニケーション」「チームワーク」「リーダーシップ」をテーマとするゲームを体験してもらい、それぞれのゲームの直後に実施する「振り返り」で各自の反省を促し、今後の意気込みを引き出しました。
作成者別アーカイブ: admin
地域活性化特別委員会担当例会を開催
11月18日(火)に地域活性化特別委員会担当の例会を開催しました。今回の例会は「日南町の地元食材の再発見と自然を体感する会」をテーマに日南町の農家レストランアメダス茶屋を会場に開催しました。
講演会では、NPO法人フォレストアカデミージャパン 理事長 狩野宏 氏を講師にお招きし、「森を活かした町づくりへの取組み」と題してご講演頂きました。講演後は「日南町の地元食材の再発見」をテーマに日南町の食材を活かしたメニューが参加者に提供されました。
鳥取県経済再生成長戦略検討委員会担当例会を開催
11月11日(火)に鳥取県経済再生成長戦略検討委員会担当の例会を開催しました。今回の例会では新潟県産業労働観光部 参与 河合 雅樹 氏に「健康ビジネスによる地方産業の高付加価値化 新潟県健康ビジネス連峰政策の例」と題して、新潟県が取組む健康ビジネスについてご講演頂きました。
日本の高齢化は世界で最も早く進んでおり、今後元気な高齢者向けの市場の拡大が見込まれ、また、世界的に見ると人口増と高齢化が進んでいるため、日本で成功したビジネスモデルが世界市場の先行例と成り得るとのことでした。このほか、今後注目すべき取組みとしてCCRC(Continuing Care Retirement Community)が講演の中で紹介されました。
総務委員会担当オープン例会を開催
鳥取大学医学部連携特別委員会担当例会を開催
国際経済委員会担当オープン例会を開催
境港活用特別委員会担当例会を開催
3月3日(火)に境港活用特別委員会の担当例会を開催しました。今回は弓ヶ浜水産㈱ 代表取締役社長 鶴岡 比呂志 氏を講師にお招きし、「美保湾における銀鮭の養殖について」というテーマでご講演頂きました。
講演終了後は茹でがに小屋を開催し、カニ、サケといった当地の食資源を体験しました。
境港活用特別委員会担当例会
・日 時:平成27年3月3日(火)17:00~19:30
・場 所:境港さかなセンター内 美なと亭
・担 当:境港活用特別委員会
・内 容:①講演会
・演 題:「美保湾における銀鮭の養殖について」
・講 師:弓ヶ浜水産㈱ 代表取締役社長 鶴岡 比呂志 氏
②今年も 今日だけ 絶品茹でがに小屋
・参加者:21名
広域観光戦略特別委員会担当オープン例会を開催

2月23日(月)大山山麓観光推進協議会主催の「とっとりスタイルエコツーリズムセミナー」に合わせて広域観光戦略特別委員会担当のオープン例会を開催しました。
鳥取県が昨年実施したマレーシアガイド研修の報告並びに日本エコツーリズム協会 理事 山田 桂一郎 氏による基調講演「お客様に選ばれる地域の魅力とは」が行われました。
またパネルディスカッションでは、山田 桂一郎 氏がファシリテーターを務め、エコツーリズムの現場で活躍する方々をパネリストに「地域活性化のための持続可能な観光振興」というテーマでそれぞれの取組の発表やこれからのエコツーリズムについての意見交換が行われました。
オープン例会 とっとりスタイルエコツーリズムセミナー
・日 時:平成27年2月23日(月)14:30~17:50
・場 所:米子全日空ホテル
・担 当:広域観光戦略特別委員会
・内 容:
①マレーシアガイド研修報告
②基調講演
・演 題:「お客様に選ばれる地域の魅力とは」
・講 師:日本エコツーリズム協会 理事 山田 桂一郎 氏
③パネルディスカッション
・テーマ:「地域活性化のための持続可能な観光振興」
・ファシリテーター:日本エコツーリズム協会 理事 山田 桂一郎 氏
・パネリスト:
㈱知床ネイチャーオフィス 代表取締役 松田 光輝 氏
NPO法人大山中海観光推進機構 理事長 石村 隆男 氏
㈲森の国 代表取締役社長 伊澤 大介 氏
・参加者:98名(当会16名)
H27年度 4月例会【4/14(火)】の開催案内(訪問先:八頭町)
標題の4月例会ですが、地域づくり委員会(井上法雄委員長)の担当により八頭町を訪問します。
すでに会員の皆様にはご案内をしていますが、申込締切日が4月8日(水)としていますので、
お早目の申し込みをお願いします。
なお、下記のとおり日程が確定しましたので、ご確認願います。
記
1 日時 平成27年4月14日(火) 13:00~20:00
2 場所 八頭町一円(丹比、八東、安部、隼、船岡、郡家)
3 例会テーマ 「合併10年の八頭町のまちづくりに学ぶ」
4 会費 5,000円(食事代として当日申し受けします。)
5 詳細スケジュール
12:50 鳥取商工会議所玄関前 出発 <マイクロバス>
13:00 鳥取駅南口(フクコ生命ビル前)出発
14:00 宿坊「光澤寺」(八頭町南)
住職 宗元英敏氏から講話を聞きます。
テーマ:お寺の未来を考える「心の授業」
15:00 丹比駅⇒矢山彫刻(矢山裕二氏)訪問⇒八東駅⇒安部駅
⇒隼駅⇒郡家駅(ぷらっと・ぴあ・やず)
*バスで移動、宗元住職に観光ガイドをしていただきます。
*見学ポイントは獅子頭彫刻修理、カンエモン桜、ニラ畑、隼駅
*矢山彫刻では矢山裕二氏から約20分間説明を受けます。
*郡家駅の「ぷらっと・ぴあ・やず」では八頭町観光協会の方に
施設を案内していただきます。
16:45 八頭町役場(郡家) 吉田英人町長と意見交換
テーマは(仮)「合併10年の八頭町のまちづくり」
17:45 バス移動⇒船岡駅
18:00 錦水割烹にて「交流会」
ゲスト:吉田町長、宗元氏、小原利一郎氏(ひよこカンパニー)
3名
19:30 修了
20:00 鳥取駅南口
20:10 鳥取商工会議所
 <光澤寺と宗元英敏住職>
<光澤寺と宗元英敏住職>
3月18日(水) 第41回島根・鳥取県経済同友会合同懇談会が開催されました。(講師:冨山和彦氏)
このたびの第41回島根・鳥取県経済同友会合同懇談会では、経済同友会(東京)の副代表幹事である
冨山和彦氏をお招きし、「地方創生 山陰はどうする?」~地方経済が甦るために必要なこと~をテーマとして講演していただきました。
冨山和彦氏の演題は「なぜローカル経済から日本は甦るのか~GとLの経済成長戦略」でありその要旨は
概ね以下のような内容でした。
出席者は、島根経済同友会 25名 鳥取県経済同友会 62名 来賓 3名 計90名でした。
冨山氏は㈱経営共創基盤(IGPI) 代表取締役CEO。(公社)経済同友会副代表幹事のほかに、国の財政投融資に関する基本問題検討委員会、税制調査会特別委員など多くの要職を務めておられるますが、今注目されている内閣官房・まち・ひと・しごと創生会議有識者としてご活躍中です。


【なぜローカル経済から日本は甦るのか】(要旨)
○ローカル経済の底上げは「賢い規制」も。 2つの思い違い
① 「中央の大企業の地方誘致が地方再生の切り札」
② 「地方再生の原動力は農林水産業と製造業」
現在の産業構造は、Gの世界とLの世界に2分される。農業も大半はLの世界。
G型産業の生産性や賃金は高いが、GDPの7割、雇用の8割はL型産業である。
L型では大半はサービス業中心、製造業は約2割に低下している。農林水産業は4%でしかない。
(農業中心の青森県でも13%にとどまっている。)
Lの中心的課題———-先進国で最低レベルのサービス産業の労働生産性と低賃金問題
(農林水産業はさらに低い実態である。)
生産性(「稼ぐ力」)向上の原動力はイノベーションと集約化、カギを握るのは「人」。
企業再生も中心市街地再生も成否を分けるのは箱モノ建設ではなく、リーダー人材の有無であり、お金を使うのであれば「ひと」に使うべきだ。
企業の新陳代謝を促し、優秀な人材が率いる高生産性・高賃金の企業へ事業と人材を集約していくこと。
高度人材の地方還流策、地元就職者の奨学金返済免除など「ひと」に重点を置いた政策は評価できる。 規制改革「地方創生特区」の活用に加えて、競争の実態を踏まえた「スマートれグレーション(賢い規制)」が重要。
○中核都市の活性化や集約へ努力の継続を
「地方在住者は『田舎暮らし』をしている」イメージは間違い
地方在住者の3割が人口30万人以上の中核都市に住む。10万人以上だと6割。
すでに地方在住者の多くは、「都会」に住み、都市型生活を営んでいる。
問題は小規模都市や中山間地部。L型のサービス産業の生産性が極めて低い。
⇒⇒社会福祉などの公共サービスコスト高、子育て世代の低賃金、病院・学校不足。
一方、東京にG型世界の高所得者が多いのは事実だが、大半はL型産業の対面型サービス業で働く
人々。年収400~500万円の若年勤労者世帯。
高い住宅費に加えて、長い通勤時間。首都圏での子育ては厳しい。
「まち」の重要課題⇒⇒地方中核都市の活性化にある。
コンパクトシティー化を推進し、適度な集積度の「まち」をつくり、稼げる仕事づくり、中所得の
「ひと」が無理なく子育てできる生活圏に人口を集約化する。
長い時間軸に耐えうる堅固な政策遂行基盤を法的、制度的に整備する必要がある。
GとLには垂直的な産業連関がないので、トリクルダウン(富の落ちこぼれ)は起きにくいと同時に、
Gの世界をたたいてもLの世界が潤うわけではない。
結局、地方創生には地域経済自身の「稼ぐ力」の向上、すなわち成長戦略に真正面から
取り組むしかない。
GとLのシナジー効果を生むこと。これから先は実行力が問われる。
*質疑応答もあり、熱心に参加者は聞き入っていました。盛会裏に終わりました。
*懇親会にも冨山氏に参加いただき、合同懇談会のメンバーと懇談していただきました。
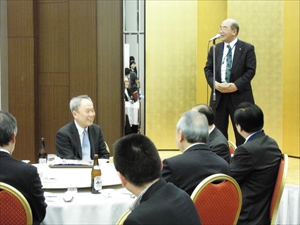

<開宴あいさつ 陶山秀樹代表幹事(島根)> <来賓あいさつ 米子市長 野坂康夫氏>