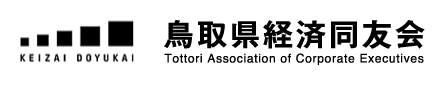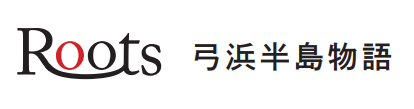3月18日(水) 第41回島根・鳥取県経済同友会合同懇談会が開催されました。(講師:冨山和彦氏)
このたびの第41回島根・鳥取県経済同友会合同懇談会では、経済同友会(東京)の副代表幹事である
冨山和彦氏をお招きし、「地方創生 山陰はどうする?」~地方経済が甦るために必要なこと~をテーマとして講演していただきました。
冨山和彦氏の演題は「なぜローカル経済から日本は甦るのか~GとLの経済成長戦略」でありその要旨は
概ね以下のような内容でした。
出席者は、島根経済同友会 25名 鳥取県経済同友会 62名 来賓 3名 計90名でした。
冨山氏は㈱経営共創基盤(IGPI) 代表取締役CEO。(公社)経済同友会副代表幹事のほかに、国の財政投融資に関する基本問題検討委員会、税制調査会特別委員など多くの要職を務めておられるますが、今注目されている内閣官房・まち・ひと・しごと創生会議有識者としてご活躍中です。


【なぜローカル経済から日本は甦るのか】(要旨)
○ローカル経済の底上げは「賢い規制」も。 2つの思い違い
① 「中央の大企業の地方誘致が地方再生の切り札」
② 「地方再生の原動力は農林水産業と製造業」
現在の産業構造は、Gの世界とLの世界に2分される。農業も大半はLの世界。
G型産業の生産性や賃金は高いが、GDPの7割、雇用の8割はL型産業である。
L型では大半はサービス業中心、製造業は約2割に低下している。農林水産業は4%でしかない。
(農業中心の青森県でも13%にとどまっている。)
Lの中心的課題———-先進国で最低レベルのサービス産業の労働生産性と低賃金問題
(農林水産業はさらに低い実態である。)
生産性(「稼ぐ力」)向上の原動力はイノベーションと集約化、カギを握るのは「人」。
企業再生も中心市街地再生も成否を分けるのは箱モノ建設ではなく、リーダー人材の有無であり、お金を使うのであれば「ひと」に使うべきだ。
企業の新陳代謝を促し、優秀な人材が率いる高生産性・高賃金の企業へ事業と人材を集約していくこと。
高度人材の地方還流策、地元就職者の奨学金返済免除など「ひと」に重点を置いた政策は評価できる。 規制改革「地方創生特区」の活用に加えて、競争の実態を踏まえた「スマートれグレーション(賢い規制)」が重要。
○中核都市の活性化や集約へ努力の継続を
「地方在住者は『田舎暮らし』をしている」イメージは間違い
地方在住者の3割が人口30万人以上の中核都市に住む。10万人以上だと6割。
すでに地方在住者の多くは、「都会」に住み、都市型生活を営んでいる。
問題は小規模都市や中山間地部。L型のサービス産業の生産性が極めて低い。
⇒⇒社会福祉などの公共サービスコスト高、子育て世代の低賃金、病院・学校不足。
一方、東京にG型世界の高所得者が多いのは事実だが、大半はL型産業の対面型サービス業で働く
人々。年収400~500万円の若年勤労者世帯。
高い住宅費に加えて、長い通勤時間。首都圏での子育ては厳しい。
「まち」の重要課題⇒⇒地方中核都市の活性化にある。
コンパクトシティー化を推進し、適度な集積度の「まち」をつくり、稼げる仕事づくり、中所得の
「ひと」が無理なく子育てできる生活圏に人口を集約化する。
長い時間軸に耐えうる堅固な政策遂行基盤を法的、制度的に整備する必要がある。
GとLには垂直的な産業連関がないので、トリクルダウン(富の落ちこぼれ)は起きにくいと同時に、
Gの世界をたたいてもLの世界が潤うわけではない。
結局、地方創生には地域経済自身の「稼ぐ力」の向上、すなわち成長戦略に真正面から
取り組むしかない。
GとLのシナジー効果を生むこと。これから先は実行力が問われる。
*質疑応答もあり、熱心に参加者は聞き入っていました。盛会裏に終わりました。
*懇親会にも冨山氏に参加いただき、合同懇談会のメンバーと懇談していただきました。
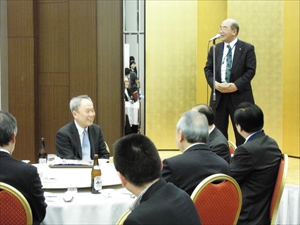

<開宴あいさつ 陶山秀樹代表幹事(島根)> <来賓あいさつ 米子市長 野坂康夫氏>