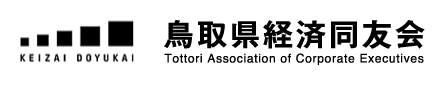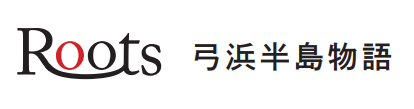掲載日:2014/10/06
第112回西日本経済同友会会員合同懇談会が開催されました。 (10月3日)
10月3日~4日にかけて第112回西日本経済同友会合同懇談会が、土佐経済同友会のお世話で高知県高知市(ザ クラウンパレス新阪急高知)で開催されました。
参加者は県外237名、土佐120名の計357名となりました。(鳥取県からは2名)
【開催趣旨】
一昨年前の安部政権発足以来、失われた20年の長きにわたるデフレ時代から脱却し、ようやく未来への明るい展望がもてるような状況となったが、地方においては、人口減少・少子高齢化の進展といった厳しい現実に中で、若年層を中心とした教育や雇用面の不均衡、都市と地方の不均衡など克服すべき課題が山積している。
2020年の東京オリンピック招致は日本国民にとって非常に喜ばしいことではあるが、一方で、東京一極集中が強まっていくことが懸念されている。
このような時代にあって、土佐経済同友会は大都市とは対極にある高知において「独自の価値観」を醸成し、磨き上げ、「日本一の幸福実感県」を目指している。
土佐経済同友会のこうした取り組みを西日本18経済同友会に広く知ってもらうためメインテーマを「高知家が育む県民幸福度(GKH)~日本一の輝く田舎を目指して」とした。
 |
| 高知駅前「土佐勤王党」3名の銅像 |
合同懇談会の開催の前に、西日本経済同友会代表幹事会が開催され、
①第2回西日本経済同友会代表者会議は平成27年7月17日(金)京都開催
②第113回西日本経済同友会合同懇談会は平成27年10月16日(金)~17日(土)奈良開催 となることが承認された。
 |
 |
| 京都経済同友会 増田寿幸代表幹事 | 代表幹事会全景 |
 |
 |
| 奈良経済同友会 山田善久代表幹事 | 【開会挨拶】土佐経済同友会 中澤陽一代表幹事 |
【基調講演】
講師:京都大学 こころの未来研究センター 准教授 内田 由紀子氏
テーマ:「日本の地域における幸福感」
内田由紀子氏は宝塚市出身だが、夫は高知市内出身、その縁で夫から後押しされて来たとのこと。
①経済成長が人々の幸せに結びついていない。
・イースターリンの幸福のパラドックス
・メキシコ・ベネゼーラ・ブラジルなどGDPが低くても幸福度が高い
②日本の幸福はなぜ低いのか
・日本社会不幸説——自由選択に乏しい。働く時間が長すぎる。格差が広がっている。夢や希望が ない。
・日本人無感覚論——悲観的日本論(そもそも幸せだとその人の人生評価は無い)
・もともと「幸福」とはこうあるべきだという「価値観」が世界全体で一元化していない。
③日本と北米とでは、「幸福観」が全く違う。文化の差か?
・日本人が「幸福」だと思うときは、お風呂に入った時と寝る前
・東洋での幸福感は山あり谷ありの変化の中にあり、アメリカ人は人生は目標に向かって登りつめ た時に感じている。
④文化差から生じているのか?
・生業(農耕VS牧畜、コメ作VS麦作)
・人口移動 ・風土・環境・気候
⑤文化の背景にある人間観
・相互独立的自己観—–ヨーロッパ系アメリカ
・相互協調的自己感—–日本
⑥政策としの「幸福」のあり方とは?
・ビジョンの重要性
・住民を巻き込んだ幸せづくり
・内閣府「幸福度に関する研究会」社会学・経済学・社会公共政策・心理学
・日本的な指標づくりに挑む—–「経済社会状況」「心身の健康」「関係性」
・幸福度は単純なランキングでは危険、まちづくりにおいてはビジョンが大切
⑦法政大学の調査
・指標の一例 出席率、持家数、畳数、保育所定員比率、離職率、労働時間、正社員比率、 休憩時間、医師数、など
・その中で高知はブービーの46位、最下位は大阪
⑧ブータンのGNH(Gross National Happiness)
・第4代国王が「幸福」を重視する政策(1970年代)
・国づくりの目標としてGNH。GNH省もあり、国立ブータン研究所と政策立案
・9つの柱を基本とするビジョンの提示と法律への反映
⑨ブータンが「幸福の国」として注目されるか?
・GDPではなく、GNH 2013年のGDP 日本は世界第3位 ブータンは162位
・ブータン仏教の精神、足るを知る精神、文化の保全と伝統
・東京都荒川区でも開始 GAH
⑩「高知家の家族会議」始動
・2011年に土佐経済同友会が提唱
・この8月に家族会議発足
・経済指標にとらわれず、豊富な自然や食、明るい県民性を評価する指標づくり
⑪個人主義の高知
・相手に干渉せず、尊重する
・温かさと他者を受け入れる風土 「いごっそう」「はちきん」
・自由思想に基づく決定の尊重・自由参加
・楽天的・ポジティブ
<まとめと展望>
①地域・職場のあり方とGNH——–GNHみんなでつくる幸せ社会へ 草郷・平山(2011年)
②豊かさの変化
・これまでは企業活動の中で、豊かな自然環境や趣味、家族や地域とのつながりを手放していた。
・企業・地域活動は幸福をもたらすものである。
・見えない価値を見える価値へ、働くことを通して生き甲斐の提供
③企業の幸福度→信頼・誇り・連帯感の基盤は「企業理念・風土の共有」ではないか?
④幸福は相対的かつ総体的なもの
・良いこと、悪いことの足し算・引き算ではない
・何を重視するのか?重みは文化や社会で異なる
・ビジョンを明確にして、それを共有することが重要
・モデルが必要
⑤個の幸福を超えて「集合的幸福」の重要性
・日本ではバランス志向性や関係性(自然、地域、家族、組織)
・集合的幸福:持続可能な社会へ発想の転換
・地域・組織はこれからの日本の幸福を支える。
講師:京都大学 こころの未来研究センター 准教授 内田 由紀子氏
テーマ:「日本の地域における幸福感」
内田由紀子氏は宝塚市出身だが、夫は高知市内出身、その縁で夫から後押しされて来たとのこと。
①経済成長が人々の幸せに結びついていない。
・イースターリンの幸福のパラドックス
・メキシコ・ベネゼーラ・ブラジルなどGDPが低くても幸福度が高い
②日本の幸福はなぜ低いのか
・日本社会不幸説——自由選択に乏しい。働く時間が長すぎる。格差が広がっている。夢や希望が ない。
・日本人無感覚論——悲観的日本論(そもそも幸せだとその人の人生評価は無い)
・もともと「幸福」とはこうあるべきだという「価値観」が世界全体で一元化していない。
③日本と北米とでは、「幸福観」が全く違う。文化の差か?
・日本人が「幸福」だと思うときは、お風呂に入った時と寝る前
・東洋での幸福感は山あり谷ありの変化の中にあり、アメリカ人は人生は目標に向かって登りつめ た時に感じている。
④文化差から生じているのか?
・生業(農耕VS牧畜、コメ作VS麦作)
・人口移動 ・風土・環境・気候
⑤文化の背景にある人間観
・相互独立的自己観—–ヨーロッパ系アメリカ
・相互協調的自己感—–日本
⑥政策としの「幸福」のあり方とは?
・ビジョンの重要性
・住民を巻き込んだ幸せづくり
・内閣府「幸福度に関する研究会」社会学・経済学・社会公共政策・心理学
・日本的な指標づくりに挑む—–「経済社会状況」「心身の健康」「関係性」
・幸福度は単純なランキングでは危険、まちづくりにおいてはビジョンが大切
⑦法政大学の調査
・指標の一例 出席率、持家数、畳数、保育所定員比率、離職率、労働時間、正社員比率、 休憩時間、医師数、など
・その中で高知はブービーの46位、最下位は大阪
⑧ブータンのGNH(Gross National Happiness)
・第4代国王が「幸福」を重視する政策(1970年代)
・国づくりの目標としてGNH。GNH省もあり、国立ブータン研究所と政策立案
・9つの柱を基本とするビジョンの提示と法律への反映
⑨ブータンが「幸福の国」として注目されるか?
・GDPではなく、GNH 2013年のGDP 日本は世界第3位 ブータンは162位
・ブータン仏教の精神、足るを知る精神、文化の保全と伝統
・東京都荒川区でも開始 GAH
⑩「高知家の家族会議」始動
・2011年に土佐経済同友会が提唱
・この8月に家族会議発足
・経済指標にとらわれず、豊富な自然や食、明るい県民性を評価する指標づくり
⑪個人主義の高知
・相手に干渉せず、尊重する
・温かさと他者を受け入れる風土 「いごっそう」「はちきん」
・自由思想に基づく決定の尊重・自由参加
・楽天的・ポジティブ
<まとめと展望>
①地域・職場のあり方とGNH——–GNHみんなでつくる幸せ社会へ 草郷・平山(2011年)
②豊かさの変化
・これまでは企業活動の中で、豊かな自然環境や趣味、家族や地域とのつながりを手放していた。
・企業・地域活動は幸福をもたらすものである。
・見えない価値を見える価値へ、働くことを通して生き甲斐の提供
③企業の幸福度→信頼・誇り・連帯感の基盤は「企業理念・風土の共有」ではないか?
④幸福は相対的かつ総体的なもの
・良いこと、悪いことの足し算・引き算ではない
・何を重視するのか?重みは文化や社会で異なる
・ビジョンを明確にして、それを共有することが重要
・モデルが必要
⑤個の幸福を超えて「集合的幸福」の重要性
・日本ではバランス志向性や関係性(自然、地域、家族、組織)
・集合的幸福:持続可能な社会へ発想の転換
・地域・組織はこれからの日本の幸福を支える。

|
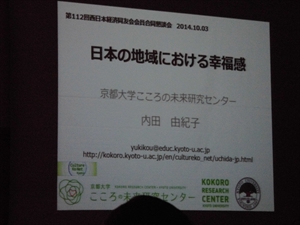
|
| 京都大学 内田 由紀子 准教授 | テーマ:「日本の地域における幸福感」 |
【パネルディスカッション】
<パネリスト>
内田 由紀子
渋谷 康一郎(筑波総研調査部長チーフエコノミスト)
黒笹 慈幾(南国生活技術研究所 代表)
安藤 桃子(映画監督)
木村 祐二(土佐経済同友会 特別顧問)
<コーディネータ>
受田 浩之(高知大学副学長)
≪内容のメモ≫
・高知って外国?ヘイと言ったらヘイと返ってくる。
・渋谷レポートがGKHの基となった。
・渋谷レポートは渋谷康一郎氏が高知の日銀時代に作成したもの。地元に足を運び、住民と繰り返し 繰り返し話をしてまとめた。高知の人が弱みだと思っていたこと(東京の人が嫌うこと)が実は、これこ
そが価値があるものだと気付いた。
・人・物・金に選択と集中、総花的でないきらりと光るもの→それは「日本一のいなか」を目標にすること
→それを実現すること→それを自慢の種にすること→それで「幸福」を感じる
・環境・自然・健康・安心・安全・伝統文化・癒し→これこそが地域ブランド→郷土愛、人と人との「ふれ
あい」を大切にする文化→「絆」の文化、高知にいれば、いつでもハグされている気持ちになる。
・木村氏——–渋谷レポートから幸福実現10年ビジョンを作成。行政の使命だが、行政が考えているこ とと経済人が考えていることとはミスマッチがある。幸福の指標づくりのため今年8月から「GKH県民 会議」を開催する運びとなった。
・内田氏——ブータン国は人口75万人、高知とほぼ一緒。ブータン国の面積は九州とほぼ同じ。
・木村氏——GKHは各市町村ちがったものでいい。NO1でなく、オンリーワンを目指すもの。各地域地
域で光耀くものを見出す。
・黒笹——–私はIターン組。東京生まれだが、小学館を退職してから高知に移住している。よそ者の目で 高知を見ている。高知は日本語が通じる外国である。たとえると、マレーシアかな? おかしなシルバーIターンなのです。高知はGDPは最下位だけど、「貧乏だけど、貧しくない」。この いごごちの良さは何なのか分からない。これを「見える化」することが重要。
・安藤——-幸せって「お金」では買えないものがある。高知は太平洋しかみていない。「日本一」ではな
く「世界一のいなか」なのでは?日本人として民族のほこりを持って世界と付き合っている。
・木村——あなたは「高知」に対して「誇り」「愛情」を持ってますか?と問いかける。仕事への満足度は 「お金」のベースがあってこそ得られるもの。「地域とのつながり」もそこから始まる。
・内田—-「幸せ」の実感は「地域とのつながり」との中にある。隣の人を信頼できるか?助けられるか?
「つながり」の指標をもつこと。
・渋谷—–大事なことだが、アンケートを毎年やってみること。「幸せ」がどういうものなのか調査する。
無いと何が困るのか?それも必要。戸別訪問でアンケート調査。アンケーの質問の精査も必要。
きっと、WIN-WINの関係がでてくる。指標を解析すること。定点観測も。
・安藤——高知の人は「芝居」がうまい。コミュニケーション能力に長けている。
・黒笹——GKHをうまく使えば、地産外商となる。県外に出ている人にも適用できる。県外者を束ねる
装置としてのGKH。「幸せの地産外商」。
・渋谷——GKHをビジネスにつなげることが大切である。物心両面、「働ける」ことがベースである。
地方創生の提言につなげること。それが高知のブランドになる。
・内田——流出している人にもアンケート調査することが必要。何を高知に求めているのか、あるいは、
何で高知に貢献したいのかとか?(受田—–内田先生にアンケートや指標を作ってもらいたい。)
・木村——-今日明日でできるものは無いが、賛同者とともにゆっくりとじっくりと「家族会議」で話し合っ
ていくこととしたい。
<パネリスト>
内田 由紀子
渋谷 康一郎(筑波総研調査部長チーフエコノミスト)
黒笹 慈幾(南国生活技術研究所 代表)
安藤 桃子(映画監督)
木村 祐二(土佐経済同友会 特別顧問)
<コーディネータ>
受田 浩之(高知大学副学長)
≪内容のメモ≫
・高知って外国?ヘイと言ったらヘイと返ってくる。
・渋谷レポートがGKHの基となった。
・渋谷レポートは渋谷康一郎氏が高知の日銀時代に作成したもの。地元に足を運び、住民と繰り返し 繰り返し話をしてまとめた。高知の人が弱みだと思っていたこと(東京の人が嫌うこと)が実は、これこ
そが価値があるものだと気付いた。
・人・物・金に選択と集中、総花的でないきらりと光るもの→それは「日本一のいなか」を目標にすること
→それを実現すること→それを自慢の種にすること→それで「幸福」を感じる
・環境・自然・健康・安心・安全・伝統文化・癒し→これこそが地域ブランド→郷土愛、人と人との「ふれ
あい」を大切にする文化→「絆」の文化、高知にいれば、いつでもハグされている気持ちになる。
・木村氏——–渋谷レポートから幸福実現10年ビジョンを作成。行政の使命だが、行政が考えているこ とと経済人が考えていることとはミスマッチがある。幸福の指標づくりのため今年8月から「GKH県民 会議」を開催する運びとなった。
・内田氏——ブータン国は人口75万人、高知とほぼ一緒。ブータン国の面積は九州とほぼ同じ。
・木村氏——GKHは各市町村ちがったものでいい。NO1でなく、オンリーワンを目指すもの。各地域地
域で光耀くものを見出す。
・黒笹——–私はIターン組。東京生まれだが、小学館を退職してから高知に移住している。よそ者の目で 高知を見ている。高知は日本語が通じる外国である。たとえると、マレーシアかな? おかしなシルバーIターンなのです。高知はGDPは最下位だけど、「貧乏だけど、貧しくない」。この いごごちの良さは何なのか分からない。これを「見える化」することが重要。
・安藤——-幸せって「お金」では買えないものがある。高知は太平洋しかみていない。「日本一」ではな
く「世界一のいなか」なのでは?日本人として民族のほこりを持って世界と付き合っている。
・木村——あなたは「高知」に対して「誇り」「愛情」を持ってますか?と問いかける。仕事への満足度は 「お金」のベースがあってこそ得られるもの。「地域とのつながり」もそこから始まる。
・内田—-「幸せ」の実感は「地域とのつながり」との中にある。隣の人を信頼できるか?助けられるか?
「つながり」の指標をもつこと。
・渋谷—–大事なことだが、アンケートを毎年やってみること。「幸せ」がどういうものなのか調査する。
無いと何が困るのか?それも必要。戸別訪問でアンケート調査。アンケーの質問の精査も必要。
きっと、WIN-WINの関係がでてくる。指標を解析すること。定点観測も。
・安藤——高知の人は「芝居」がうまい。コミュニケーション能力に長けている。
・黒笹——GKHをうまく使えば、地産外商となる。県外に出ている人にも適用できる。県外者を束ねる
装置としてのGKH。「幸せの地産外商」。
・渋谷——GKHをビジネスにつなげることが大切である。物心両面、「働ける」ことがベースである。
地方創生の提言につなげること。それが高知のブランドになる。
・内田——流出している人にもアンケート調査することが必要。何を高知に求めているのか、あるいは、
何で高知に貢献したいのかとか?(受田—–内田先生にアンケートや指標を作ってもらいたい。)
・木村——-今日明日でできるものは無いが、賛同者とともにゆっくりとじっくりと「家族会議」で話し合っ
ていくこととしたい。
 |
 |
| パネルディスカッション会場 | コーディネータ 受田浩之氏 |
 |
 |
| 映画監督 安藤 桃子 氏 | 土佐経済同友会 特別顧問 木村 祐二氏 |
 |
【懇親会】
懇親会会場は、ホテルを離れて、高知城三ノ丸の特設会場で行われました。盛大な懇親会となりました。
Copyright © 2013 TOTTORI KEIZAI DOYUKAI All rights reserved.